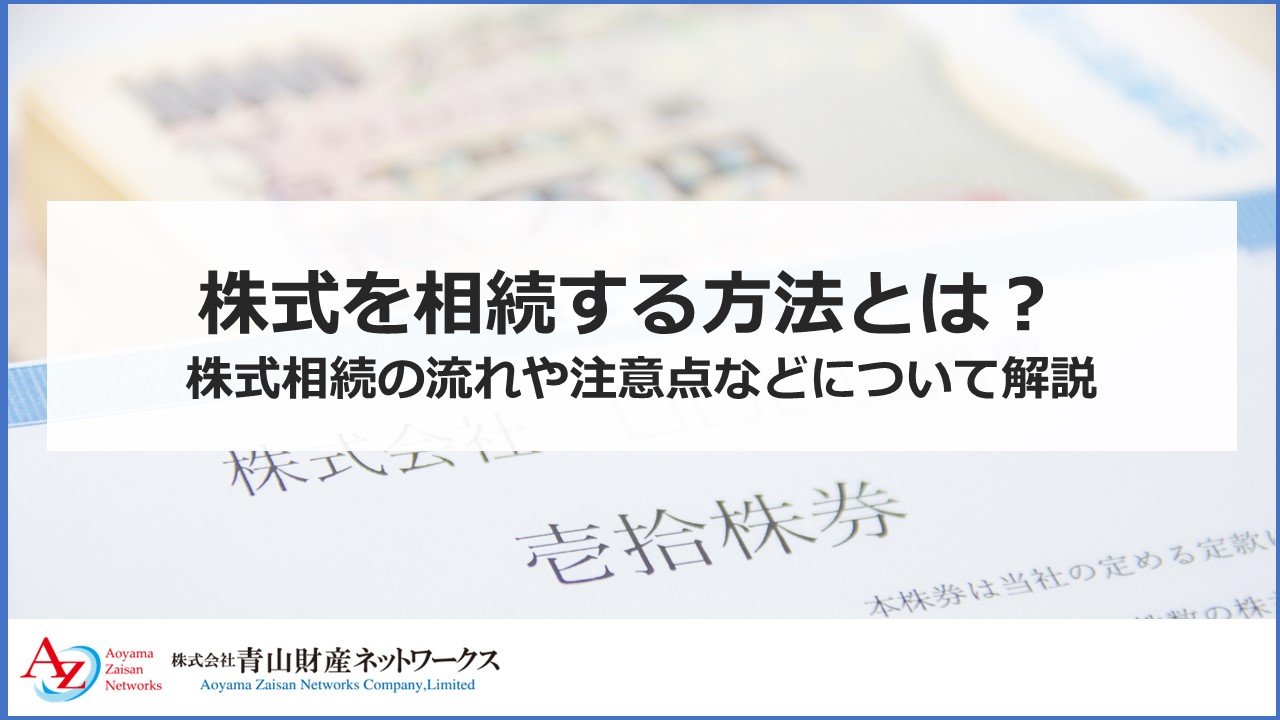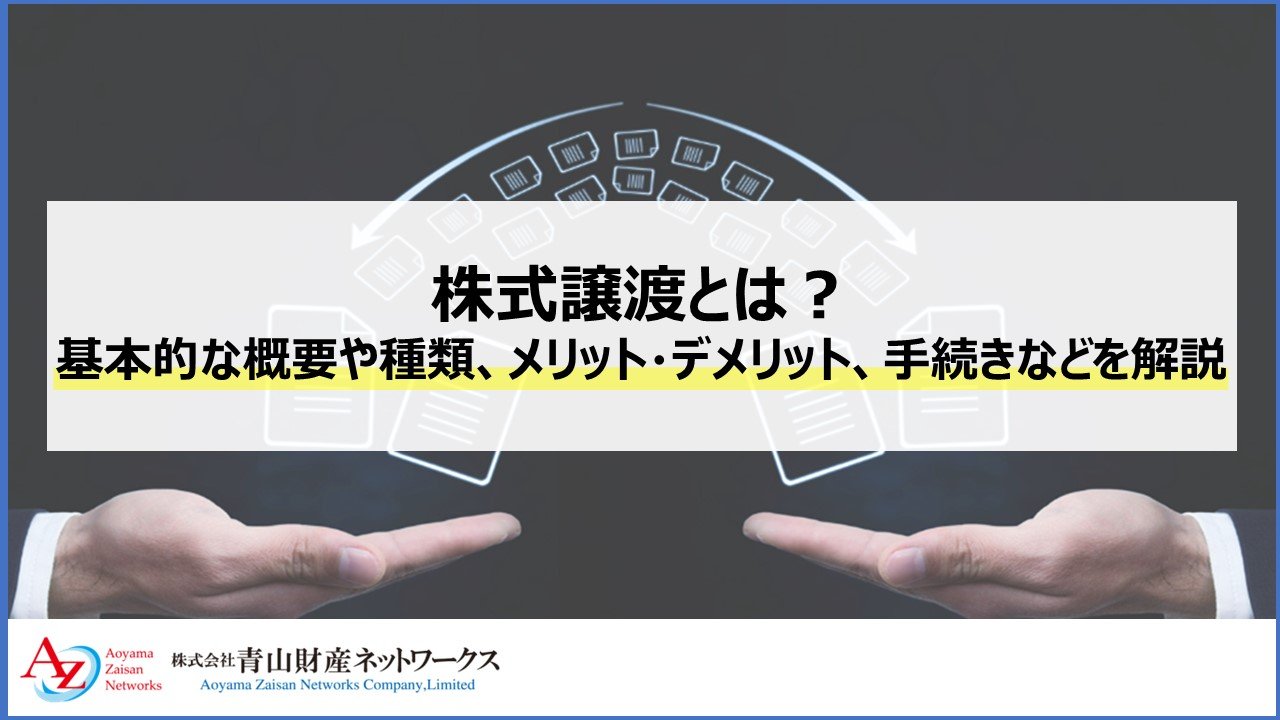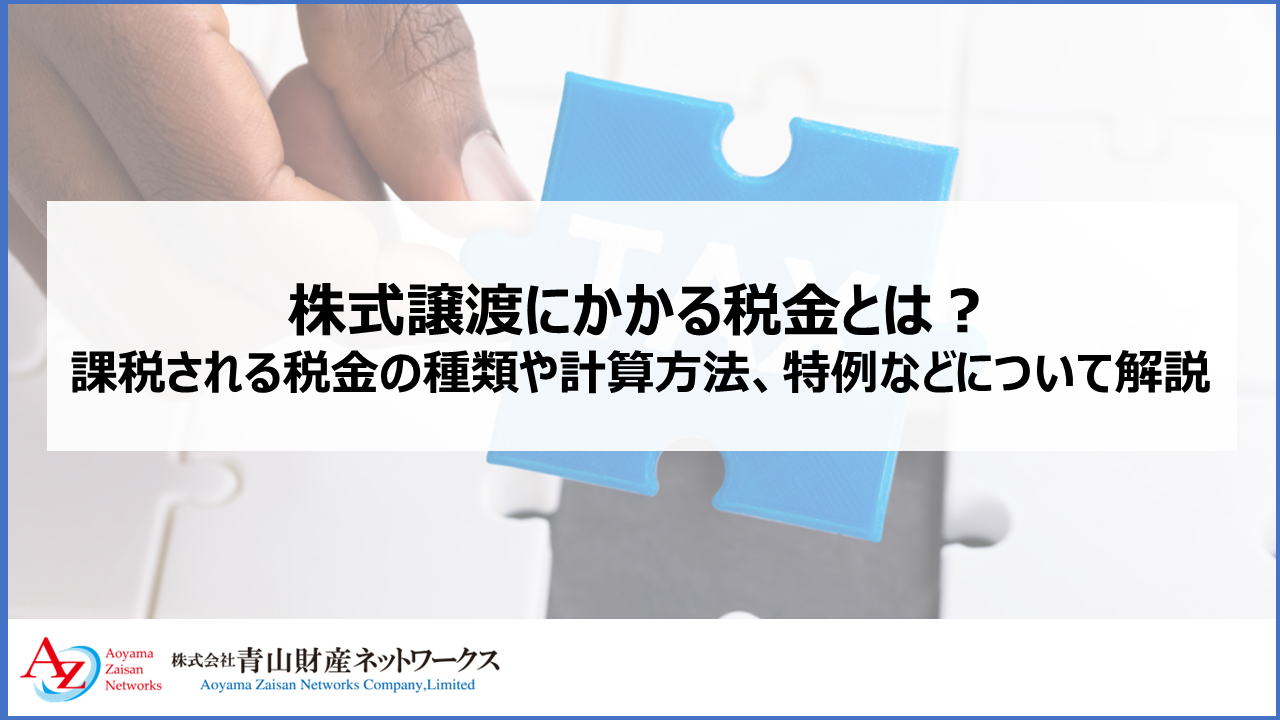株式が複数の株主に分散される「株式分散」は、企業経営において思いがけないリスクを負うことになる可能性があり、注意が必要です。
たとえば、意思決定の遅延や少数株主による経営干渉、加えて事業承継やM&Aの際に障害となることもあります。
そこで本記事では、株式分散が引き起こすリスクと対処法を詳しく解説していきます。
分散された株式の整理は予想以上に難航するケースが多く、特に株主の相続が絡むと複雑になる傾向があります。
このような事態を避けるためにも、本記事を読んで早めに対応しましょう。
株式分散とは、株主が複数いる状態
株式分散とは文字の通り、企業の株式が1人ではなく、複数の人物によって分散して保有されている状態のことです。
業歴が長い企業や規模の大きい企業は、株式が分散するのは珍しくありません。
一方で非上場の中小企業は、オーナーが全株式を保有する形態が一般的ですが、相続などにより株主が複数存在するケースもあります。
株式分散がもたらす6つの経営リスク
株式分散は、以下の6つの経営リスクが生じます。
- 会社の意思決定が遅延・停滞する
- 経営権の不安定化
- 株主管理の事務負担が増加する
- 事業承継税制を活用できない
- M&Aの障害になる
- 株式買取に資金がかかる
株主は会社法にて「会社の所有者」と定められているため、株主が複数人存在すると権利に関する問題が生じやすくなり、経営に影響を与える可能性があります。
また、将来的な事業承継やM&Aの際も障害となったり、分散した株式を集約する際に時間や資金を要したりするので注意が必要です。
株式分散がもたらす6つのリスクをひとつずつ解説していきます。
会社の意思決定が遅延・停滞する
前述のとおり株主=会社の所有者のため、直接的に会社経営に携わっていない場合でも、株主は与えられた権利を行使することが可能です。
よって、会社の意思決定に重要な役割を担う株主総会にも、議決権を有している株主は参加する権利があります。
なお、株主総会の決議方法は、以下の3つです。
- 普通決議(1/2以上の賛成が必要)
- 特別決議(2/3以上の賛成が必要)
- 特殊決議(2/3以上または3/4以上の賛成が必要)
株式が分散している場合、特別決議や特殊決議の際に賛成が得られにくくなり、決議が遅延したり停滞したりするリスクがあります。
迅速な意思決定を妨げることに繋がるため、注意が必要です。
経営権の不安定化
株式分散が進むと意思決定の過程が複雑になるため、経営権の不安定化に繋がることがあります。
特に複数の株主が異なる意見を持つ場合は、重要な決定を迅速に進めるのが困難になるでしょう。
また、議決権や発行済株式総数の3%以上を6ヶ月以上保有する株主には、取締役の解任請求を行う権利があります。
訴えを起こしても必ず解任に繋がるわけではありませんが、経営側は慎重な対応が必要です。
さらに、役員が違法行為等をして会社に損害を与えた際に、役員の責任を追及しない場合には、株主代表訴訟が起こされる可能性があります。
1株でも保有していれば訴訟が可能(公開会社の場合、6ヶ月以上の保有要件有)なため、経営面における不安要素の1つです。
株主管理の事務負担が増加する
株主は会社の保有者として多様な権利を有しているため、会社側は権利行使に応じて逐一対処しなければなりません。
たとえば、株主が死亡し、相続によって株式が相続人へと分散した場合には、会社で管理している株主名簿を書き換える必要があります。
そのため、当該相続人に株式の相続状況を確認しなければなりません。
また、株主総会を開催する際には、一人ひとりに招集手続きを行うこととなります。
招集通知等に不備があれば会社が責任を負うこととなり、最悪の場合は株主総会の決議が取り消されてしまう可能性もあるので、十分な注意が必要です。
いずれの業務も株主の所在等が明確ならば手間は減りますが、最新の情報を把握できていない場合もあります。
つまり、株式が分散すればするほど会社への負担が増えてしまうため、注意が必要です。
事業承継税制を活用できない
事業承継税制とは、会社の後継者が取得した非上場株式等に対して、贈与税や相続税の納税猶予を受けられる制度です。
一般的に代表取締役などが後継者へ株式を贈与、もしくは相続する場合は、多額の税金が発生します。
しかし、事業承継税制を活用することで、後継者の税負担を軽減することが可能です。
ただし、適用するための要件の1つに、同族内で50%を超える議決権を保有している必要があります。
もし株式を分散させた結果、同族内での議決権が50%以下になってしまった場合には、事業承継税制の恩恵を受けられません。
(なお、事業承継税制の適用要件は議決権の保有割合のみではないため、適用を考えている方は、国税庁のサイトをご参照ください。)
M&Aの障害になる
資金調達や事業承継の手段として、M&Aによる会社売却を考えている株主および経営者もいるでしょう。
しかし、株式分散には多様なリスクがあるため、買い手側からすれば株式が集約されている状態が望ましいといえます。
実際に現在のM&A市場では、株式を集約してから譲渡することが契約に盛り込まれているケースが多いです。
よって、将来的に会社(株式)の売却を考えている場合は、前もって株式を集めておきましょう。
株式買取に資金がかかる
株式を分散させることで多くの出資者から資金を集められるメリットがある一方で、株式を収集する際は多額の資金を要します。
なお、必ずしも出資を受けた金額と同額で買い戻せるわけではありません。
分散した株式を買い取るためには、株主との間で売買契約を結び、双方合意の金額にて買い取りが成立します。
年々利益を上げて成長しているような会社や、値上がりしやすい資産(土地など)を多く所有している会社は、成長に応じて株価も上昇していきます。
そのため、株式を買い取る資金の負担が大きくなる可能性があります。
さらに非上場株式の場合は、一般的に会社の株価を参照して時価を算定するため、思いがけない出費となるケースも少なくありません。
株式分散が発生する4つの要因

株式分散が発生する要因は、主に次の4つが挙げられます。
- 相続による株式移転
- 事業関係者の自社株式保有
- 会社設立時の名義株式
- 過去の株式公開計画の影響
株式分散が発生する要因は主に相続ですが、相続人が複数人いる場合はそれだけ多岐に渡り分散することがあります。
また、ストックオプションのように自社株を従業員に付与したり、商法改正以前の名義株によって分散したりするなどさまざまです。
株式分散が発生する要因4つを、理由とともに解説していきます。
相続による株式移転
株主が死亡し相続が発生すると、保有していた株式は相続財産として引き継がれます。
一般的に相続人には配偶者や子どもが該当しますが、その分だけ株式が分散されることになります。
誰にどのくらいの株式を相続するかは分割協議や遺言書の内容にもよるものの、もし相続人が5人いれば、それぞれに相続されることも珍しくありません。
特に非上場株式のような非公開の株式は、相続や贈与によって株式が分散されるケースが多く見られます。
事業関係者の自社株式保有
役員や従業員などの事業関係者に対して、あらかじめ設定した価格で自社株を取得する権利を付与することがあります。
いわゆるストックオプション制度は、業績が向上すると株価も上昇するため、就業へのモチベーションを上げる手段として利用されています。
会社設立時の名義株式
一般的に名義株式とは、実際の所有者と株主名簿に記載されている人が異なる株式を指します。
1990年の商法改正以前は、会社設立に最低7人以上の発起人が必要だったため、出資や経営に携わっていないにも関わらず、名義のみを貸すといった行為が横行していました。
名義株を放置していると、名義人が死亡もしくは所在不明になってしまったときに、集約が困難となります。
将来的に困ることのないように、不必要な名義株は早急に対処、収集するのが望ましいでしょう。
過去の株式公開計画の影響
株式公開計画とは一般的に、証券取引所に上場することです。
不特定多数の投資家に株式を売却して資金調達を行えるほか、会社の知名度が高まることで取引先との関係の円滑化や、信用の獲得に繋がるでしょう。
ただし、資金基盤を強化するために複数の投資家に株式を売却して資金調達を行えば、当然株式が分散していきます。
そのため、過去に株式公開を計画していた場合には、株主が多岐に渡っているケースが多くあります。
株式分散を解消する4つの方法
株式分散を解消するには、以下の4つの方法が挙げられます。
- 株式の買い戻し
- 名義株式の整理と名義変更
- 株式併合による集約
- 売渡請求制度の活用
分散した株式を収集するには、株主から買い戻すことが一般的な方法です。
会社もしくはほかの株主が、算定された株価に見合った対価を支払うことで買い戻せますが、売買取引となり税金が発生するため注意しましょう。
そのほか名義の変更や株式の併合を行うことでも、株式分散を解消することが可能です。
株式分散を解消する4つの方法を、それぞれわかりやすく解説していきます。
株式の買い戻し
分散してしまった株式は、株主から買い戻すか、協力的な株主である場合は贈与による収集も可能です。
買い戻すには会社(法人)が自社株として買い取るか、ほかの株主(個人)が買い取る方法があります。
ただし、株主から売買価格の同意が得られず、交渉が難航することも考えられます。
また、時価よりも著しく低い価格で買い戻す、もしくは贈与を受ける場合には、贈与税(法人は受贈益)が課せられる可能性があるため、取引金額は慎重に決めましょう。
名義株式の整理と名義変更
1990年の商法改正以前に会社が設立されている場合には、出資者と名義が一致していない株式(いわゆる名義株式)が存在している可能性があります。
現在は会社法が改正され、1人以上の発起人がいれば会社を設立できるため、社長名義へ変更するのがよいでしょう。
また、名義人の所在および連絡先が確認できる場合は、一定の手続きを踏むと名義変更が可能です。
なお、所在や連絡先が不明の場合でも、所在不明株主の株式売却制度を利用すると、名義株式を収集できます。
名義株式の保有者は形式的な株主にすぎず、放置していてもデメリットが生じるため、早急な対応を検討しましょう。
株式併合による集約
株式併合とは、複数の株式を1株にまとめる手続きで、少数株主の保有株式数を1株未満にすることが可能です。
たとえば「5株を1株に併合する」という決議がなされた場合、4株保有していた株主は1株未満になります。
株価自体は上昇しますが、株式数が減るため、結果的に株主の財産価値に変動はありません。
株式併合は少数株主を整理し、会社の株式構成を集約できるため、株式分散の解消にも役立つでしょう。
ただし、この手続きを行うには、株主総会で2/3以上の賛成を得る必要があります。
さらに、裁判所への売却申請が必要なため、手続きには時間がかかることを考慮しておきましょう。
売渡請求制度の活用
売渡請求制度も少数株主から株式を強制的に買い取る、スクイーズアウトの一種です。
特別支配株主(議決権の90%以上を有する株主)であれば、適切な売買価格を少数株主に通知して、一方的に株式を買い取れます。
売買価格は適正でなければなりませんが、少数株主の同意を得る必要はありません。
特別支配株主でなければ活用できない制度ですが、株主総会を開催する必要がないため、手続きの手間を省けるのが特徴です。
株式分散を防ぐ事前対策

株式分散が発生する主な要因は相続のため、事前の計画的な遺言書の作成が有効です。
遺言書を活用することで、意図しない株式の分散を防げます。
そのほか、種類株式を活用して株式分散を防ぐ方法も紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
計画的な遺言の活用
相続時の株式分散を防ぐには、遺言を活用する方法があります。
遺産の分割協議によって株式を特定の相続人に引き継ぐことは可能ですが、遺言には法的効力があるので、株式分散を防ぐことが可能です。
ただし、遺言がある場合でも遺留分は侵害できません。
遺留分とは民法により定められた制度で、法定相続人が最低限相続できる相続分のことです。
侵害するとトラブルに発展する恐れがあるため、遺言を作成する際は遺留分を考慮した内容にすることが重要になります。
種類株式の導入
種類株式とは、付与される権利が平等な普通株式とは異なり、あらゆる特典あるいは制約が付与された株式のことです。
種類株式の形態は9つありますが、ここでは株式分散の解消に効果的な4つの株式について解説していきます。
譲渡制限株式
譲渡制限株式とは、会社の承認がなければ他者に譲渡できない株式のことです。
少数株主が自由に株式を譲渡するのを防ぐだけでなく、会社に不利益をもたらす可能性のある第三者への譲渡を事前に防げます。
現在の日本の中小企業では広く採用されており、メジャーな形態のひとつとして挙げられます。
取得条項付株式
取得条項付株式とは、定款に記載された一定の事由が生じた際に、会社が株主の同意を必要とせずに買い取れる株式のことです。
会社によって規定する内容は異なりますが、上場が決定した場合や、任意の年月日が到来した場合などが挙げられます。
あらかじめ条件を定められるため、株式の分散を防ぐことが可能です。
議決権制限株式
議決権制限株式とは、株主総会における議決権の行使を一部もしくは全て制限された株式のことです。
議決権制限株式を活用することで経営への影響をコントロールできるため、会社の意思決定が困難になるリスクを防ぐことが可能です。
株主からすれば経営に干渉できなくなりますが、配当の利益は享受できます。
拒否権付株式
拒否権付株式とは、株主総会などの決議に対して拒否権が付与された株式を指し、「黄金株」とも呼ばれています。
直接的な株式分散の抑制には繋がりませんが、重要な決議に対して拒否権を持つため、重要な意思決定への影響力を維持することは可能です。
ただし、あまりに強力な権限であり、株主の平等性を侵害するという考えから、上場企業では採用されることが滅多にありません。
まとめ|株式分散は計画的な対処が必要
株式分散が引き起こすリスクは多岐にわたり、最悪の場合経営権までも脅かされる恐れがあります。
特に株主が増えて経営方針に対する意見が分かれると、会社の意思決定が遅れたり停滞したりするリスクが生じるため、気を付けましょう。
一度分散してしまった株式を集約するためには、多くの時間や資金、さらには事務的労力が必要です。
そのため、株式の分散が発生する前に慎重な判断と適切な対応が求められます。
株式分散の問題に関しては、税理士などの専門家に相談しながら進めるのも有効です。
専門的なアドバイスを受けることで、株式分散解消に向けた適切な対応策を講じることができるでしょう。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~