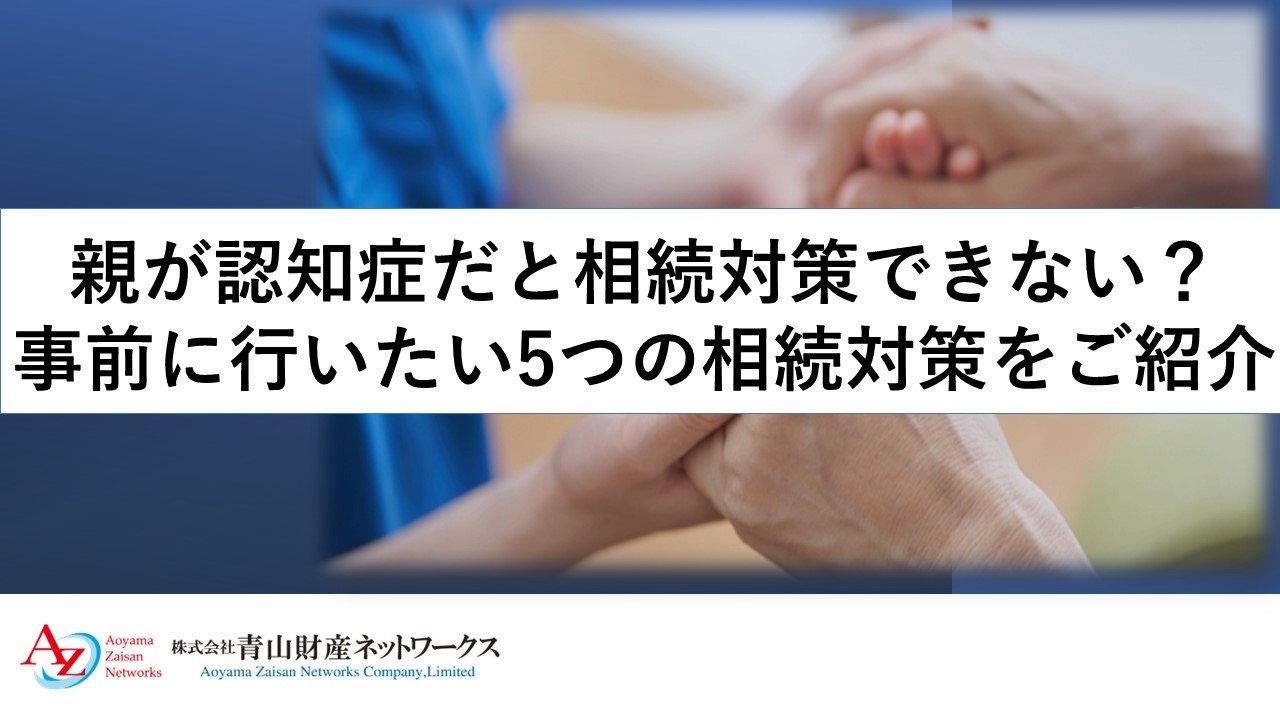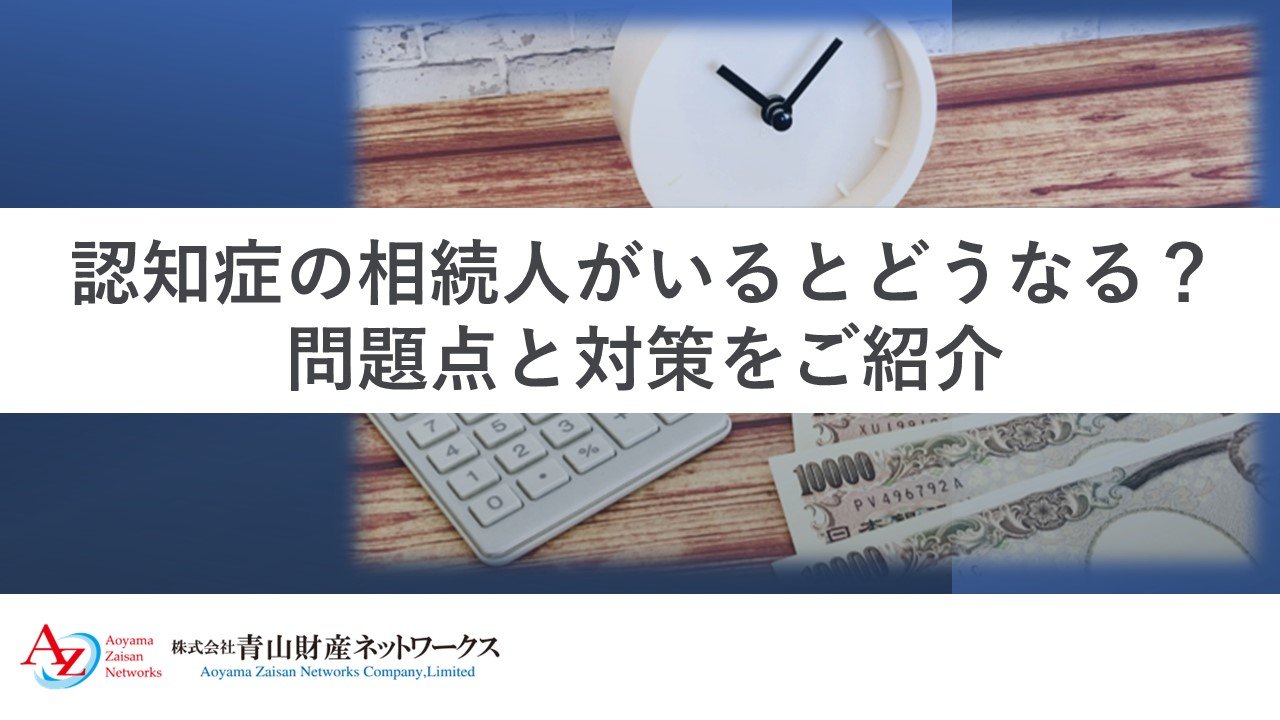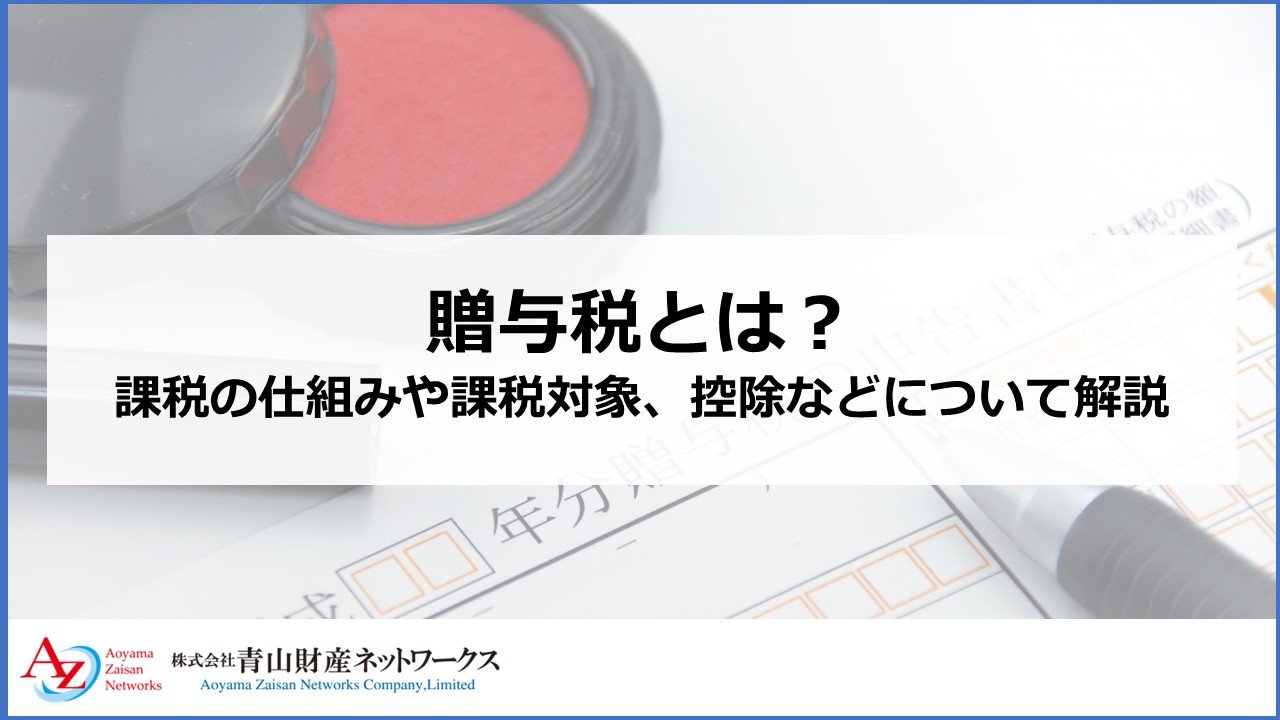親が認知症を患い、意思能力が喪失した状態と医師から診断されると財産の管理が難しくなるため、事前に対策を考えておく必要があります。
例えば「銀行口座が凍結される」ことや「介護費用を捻出するために自宅を売却する」といったことができなくなることにより、財産を自由に使えなくなる可能性があり、その結果親の生活費・医療費・介護費用の調達に困ってしまうケースが想定されます。
こうした場合には、成年後見制度を利用して財産管理を行うことが一つの方法です。
とはいえ認知症が軽度であれば、成年後見制度以外の方法で財産管理を行う選択肢も想定されます。
そこで本記事では、親が認知症を患った場合に直面する財産管理の問題と、症状の進行具合に応じた財産管理方法について解説します。
親が認知症になることで起こる相続と財産管理の課題
この章では親が認知症になることで起こり得る相続と財産管理の課題について解説します。
相続の準備が進められなくなる
認知症の方が遺言書を作成した場合、その遺言書が無効と判断される可能性があります。遺言書の有効性は、遺言者が遺言を作成する時点で意思能力を有していたかどうかに基づいて個別に判断されます。
特に法定相続分とは異なる配分を希望する場合や、分割が難しい財産が遺産に含まれる場合、遺言書が無効となると希望どおりの遺産分割が難しくなることがあります。
生前贈与も財産を贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の間で契約が成立する必要があるため、贈与者に意思能力がない場合は無効となります。その結果、生前贈与を利用した相続税の節税対策が行えなくなる可能性があります。
預貯金を引き出せなくなる
親が認知症になると、家族が介護や日常生活のサポートを行うことが一般的です。
例えば、食事の準備や服薬の管理、家の掃除などの基本的な日常的な支援に加えて、光熱費の支払い、生活費の管理といった金銭面でのサポートも家族が担うことが多くなります。
しかし、このような状況において、認知症の親に代わって家族が金融機関で生活費を引き出そうとする際、特に注意が必要です。窓口で事情を説明することで、場合によっては口座が凍結されてしまうことがあります。
口座が凍結されると、その後、生活費や介護費用を引き出すことができなくなり、非常に困った状況に陥る可能性があります。
つまり、認知症の親が口座の管理を自分で行えないため、家族がその代わりに手続きをしようとしても、金融機関によっては不正使用を防ぐために口座が凍結されることがあるということです。
このような事態を避けるためには、事前に金融機関に相談し、親の状況に合った手続きを取ることが重要です。正当な手続きを経ることで、スムーズに生活費を引き出せるようにする方法があります。
認知症の親が持っているキャッシュカードを無断で使って資金を引き出すことは、親の意図に反する行動と見なされるだけでなく、後々法的なトラブルに発展するかもしれません。
さらに、認知症の親の口座を管理していた家族がその後、相続人となった場合には、ほかの相続人から引き出し内容や使用目的について疑問を持たれるケースもあり得ます。
このような疑念が相続トラブルの原因となり、家族間での関係がこじれることもあるでしょう。例えば、引き出された資金がどのように使用されたのか、またその金額が適切であったかどうかが問題になることがあります。
これにより、相続手続きが複雑化し、円満な相続が難しくなる場合もあります。そのため、親の口座を管理する際には、透明性を保ち、適切な記録を残すことが求められます。
認知症の親の生活支援を行う際には、金銭面での管理や手続きについて慎重に対応する必要があります。
法的な枠組みを守りトラブルを避けるために、事前に専門家に相談することも一つの方法です。また、家族間での円滑なコミュニケーションを心がけ、後々の相続トラブルを未然に防ぐための準備をしておくことが重要といえるでしょう。
不動産を売却することが難しくなる
法律では、認知症などで意思能力を欠く方が行った売買契約は無効とされています。
例えば、一人暮らしのお母さまが認知症を発症し、ご実家での介護が困難になり、老人ホームや介護施設への入居が必要になった場合、入居費用を用意するためにご実家を売却しようとしても、認知症の方自身が不動産の売買契約を結ぶことはできません。
親が認知症になる前に取るべき相続の備え

認知症の疑いがある場合に締結した契約の有効性が争われるおそれがあります。以下の対策は事前にご家族で話し合って、早めに行動に移しましょう。
遺言書の作成
遺言は、自身の財産を死後に誰にどのように引き継ぐかを示す最終的な意思表示です。意思能力が保たれている間に、遺言書の作成を実施しましょう。
生前贈与を活用する
無償で財産を譲り渡すことを贈与といいます。例えば、父親のAさんが判断能力が十分あるうちにアパートを息子のCさんに贈与すれば、そのアパートはCさんの財産となり、Aさんが管理する必要がなくなります。
家族信託の導入
家族信託とは、財産の所有者である委託者が信頼する家族を受託者として選び、信託契約を結んだ上で、受託者がその財産の管理や処分を代行する仕組みです。
委任契約の締結
委任契約とは、簡単にいえば「委任状を書くこと」を指します。
例えば、父親であるAさんが息子のCさんに「アパートの家賃を受け取る権限」や「アパートの売買契約を締結する権限」を委任する場合、Aさんが委任状を書けば、CさんはAさんの代理人として借主に家賃を請求したり、買主を探して売買契約を結んだりすることが可能になります。
親が認知症の兆候を見せた場合にすべきこと
親から認知症の兆候を感じたら、認知症がどのような病気かを理解し、認知症についての知識を深めることが大切です。また、地域の関係機関を把握し、親に受診を促すことも重要です。
ただし、認知症が進行すると、先に挙げたようなリスクが生じるため、親が認知症を発症する前に適切な準備をしておくことをお勧めします。
認知症に関する知識を深める
認知症が進行すると、些細なことで怒りっぽくなることがあります。もし家族がその症状が認知症によるものだと理解せず、親を煩わしく感じたり、冷たく接したり、距離を置いたりすると、親の認知症はさらに悪化してしまう可能性があります。
このような悪循環を防ぐためにも、普段から家族の間で認知症に関して話し合ったり、関連書籍を読んで知識を深めたりすることが重要です。
地域のサポート機関を確認し、受診を行う
親が認知症の兆候を見せたら、認知症患者本人やその家族向けのサービスや支援にどのようなものがあるのかを把握し、早期に認知症の治療を受けられるよう準備しておくことが大切です。
地域包括支援センターへの相談
地域包括支援センターは、地域の高齢者に関する相談や支援を行う機関で、認知症患者やその家族への支援内容やサービスに関する情報を提供しています。
社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーが相談やサポートを行い、家族には介護に関するアドバイスを提供するなど、包括的なケアを行っています。
また、医療機関や介護サービス事業所などの支援機関や、利用可能な制度も紹介してくれるため、親が認知症の可能性があると感じた場合、まず地域包括支援センターへ相談することをおすすめします。
早期診断と治療の重要性
親が認知症の兆候を見せた場合は、すぐにかかりつけ医もしくは地域包括支援センターから紹介を受けた医療機関を受診するように勧めてください。早期に治療を開始することで、認知症の進行を遅らせることが期待できます。
しかし、認知症の本人が受診を拒むこともあります。その際は、親の気持ちに配慮し、「念のため病院に行くほうがよい」「健康診断を受けてみたほうがよい」など、優しく声をかけることが大切です。
財産や相続に関する事前の準備を行う
認知症の進行度合いによって状況は異なるかもしれませんが、財産管理については早期に適切な対応を取ることが大切です。
相続についての取り決めをしても、親の意思や判断能力が認められない場合、効力を持たないことがあります。
そのため、親の判断能力が失われる前に、財産管理や相続について親の意思で決定できるよう、家族全員で話し合っておくことが重要です。
親に認知症の疑いがある場合に取るべき相続の備え
この章では親に認知症の疑いがある場合に取るべき相続の備えについて解説します。これらを状況に応じて組み合わせて対策することが解決法となり得ます。
成年後見制度(法定後見)の利用
成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた人を保護するため、裁判所が後見人を選任して財産管理などを代行する仕組みです。
任意後見制度を活用する
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に、自分の財産管理や処分を任せる相手とあらかじめ契約を結んでおく仕組みです。
認知症の親の相続でトラブルを防ぐためのポイント

認知症の親が亡くなった際に発生しやすい相続トラブルの一例として、一部の相続人による遺産の不正使用が疑われるケースがあります。
認知症の親が亡くなった後に起こりやすい相続トラブルや、その場合の法的な対処方法、さらには相談先について詳しく解説します。
認知症の親の相続時に発生しやすい問題とは
認知症の親が亡くなった場合、以下のような相続トラブルに注意が必要です。
- 一部の相続人による遺産の不正使用が疑われる
- 一部の相続人が強引に相続対策を行ったのではないかと疑われる
親の介護が長期にわたった場合、遺産が予想以上に少なくなっていることが多く、特に、特定の相続人が主に介護を担当していた場合、疑惑を避けるために介護にかかった費用の証拠を残しておくことが重要です。
また、親が認知症を発症した後に遺言書を作成したり、生前贈与を行ったりした場合、それが親の真意によるものではなく、相続人が勝手に行ったものではないかと疑われることもあります。
遺言書や生前贈与が有効であると主張したい場合は、その時点で親がどれだけ判断能力を持っていたかを示す証拠を集める必要があります。
法的な対応策と相談できる窓口
一部の相続人による遺産の不正使用や、被相続人の意向に反して相続対策が行われた可能性がある場合、相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
相続問題に強い専門家であれば、必要な証拠についてアドバイスしてくれるほか、その後の遺産分割調停もサポートしてくれます。
まとめ
親が認知症になり判断能力を失うと、親名義の財産を管理することが難しくなります。親自身が財産を管理したり処分したりすることができなくなるだけでなく、子どもや親族が親名義の財産を活用したり売却したりすることもできなくなる点に注意が必要です。
その場合には、成年後見制度を利用して、成年後見人に親の財産管理を任せるようにしましょう。
一方、認知症が軽度であれば、家族信託や任意後見制度といったほかの制度を利用することが可能な場合があります。 認知症の進行には個人差があり、急速に症状が悪化することもありますので、これらの方法を選ぶ場合は、早期に手続きを進めることが重要です。家族信託や任意後見制度の手続きは複雑であるため、専門家に相談することをおすすめします。
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策