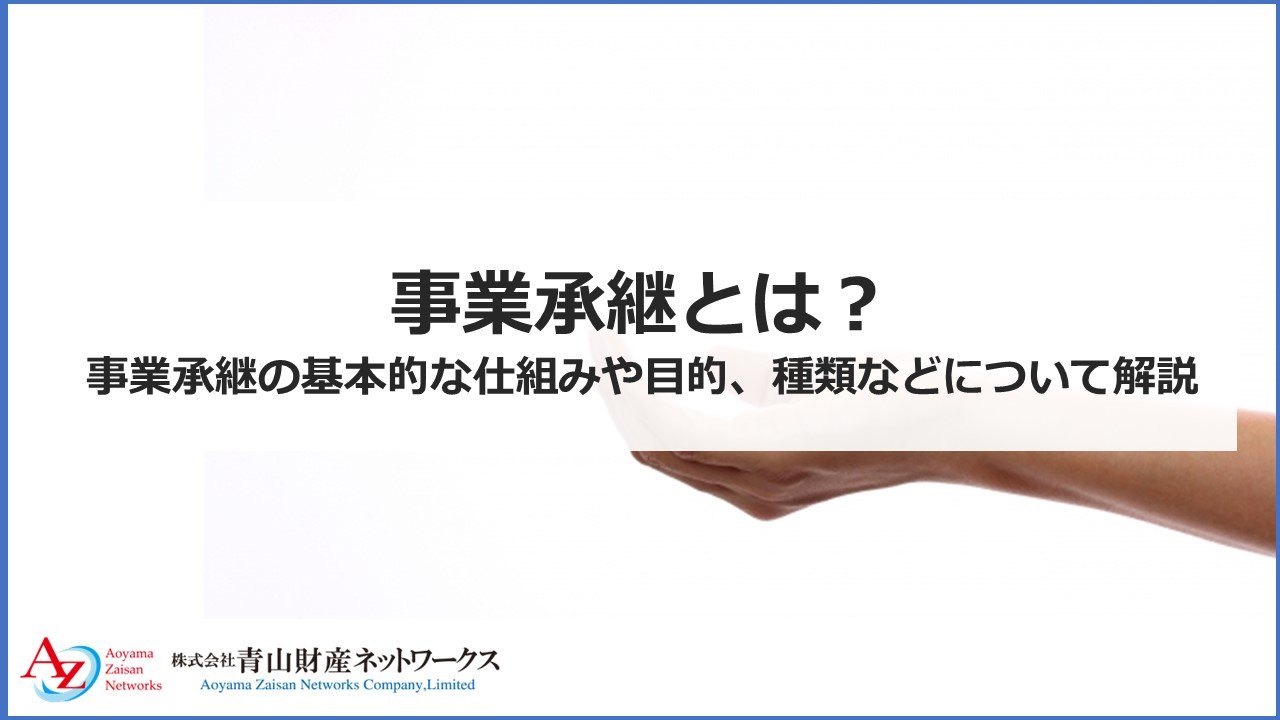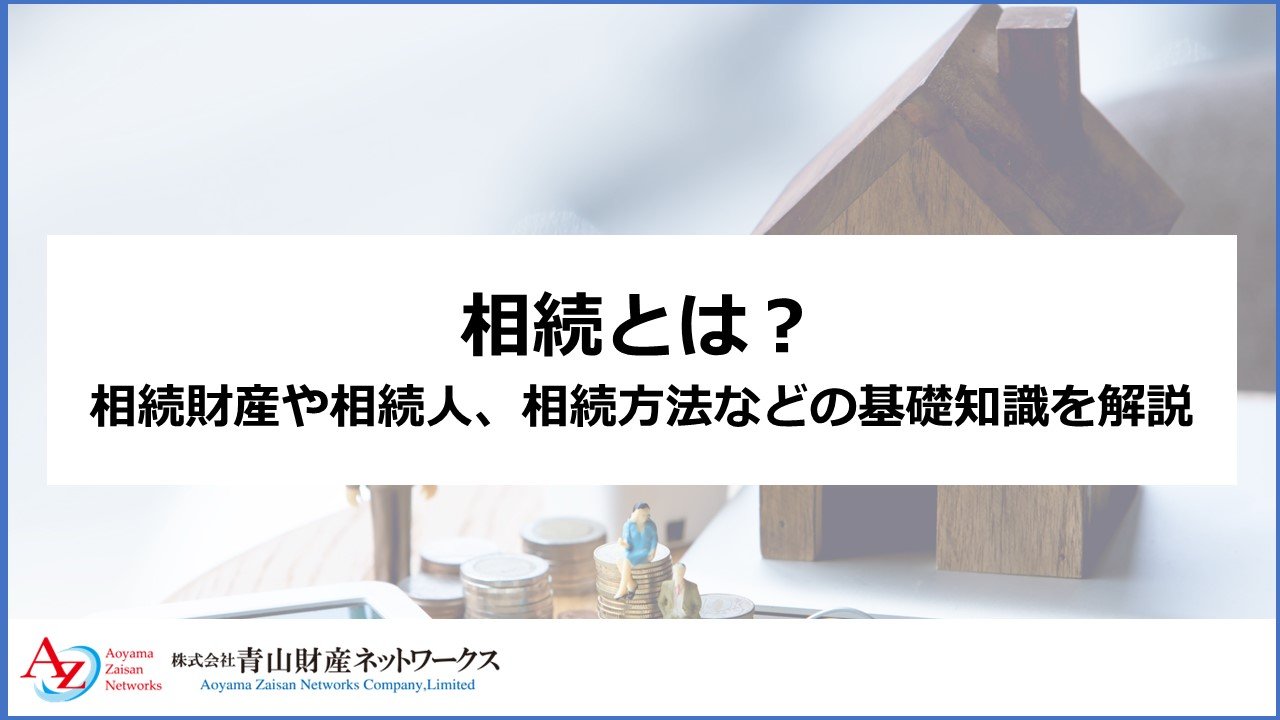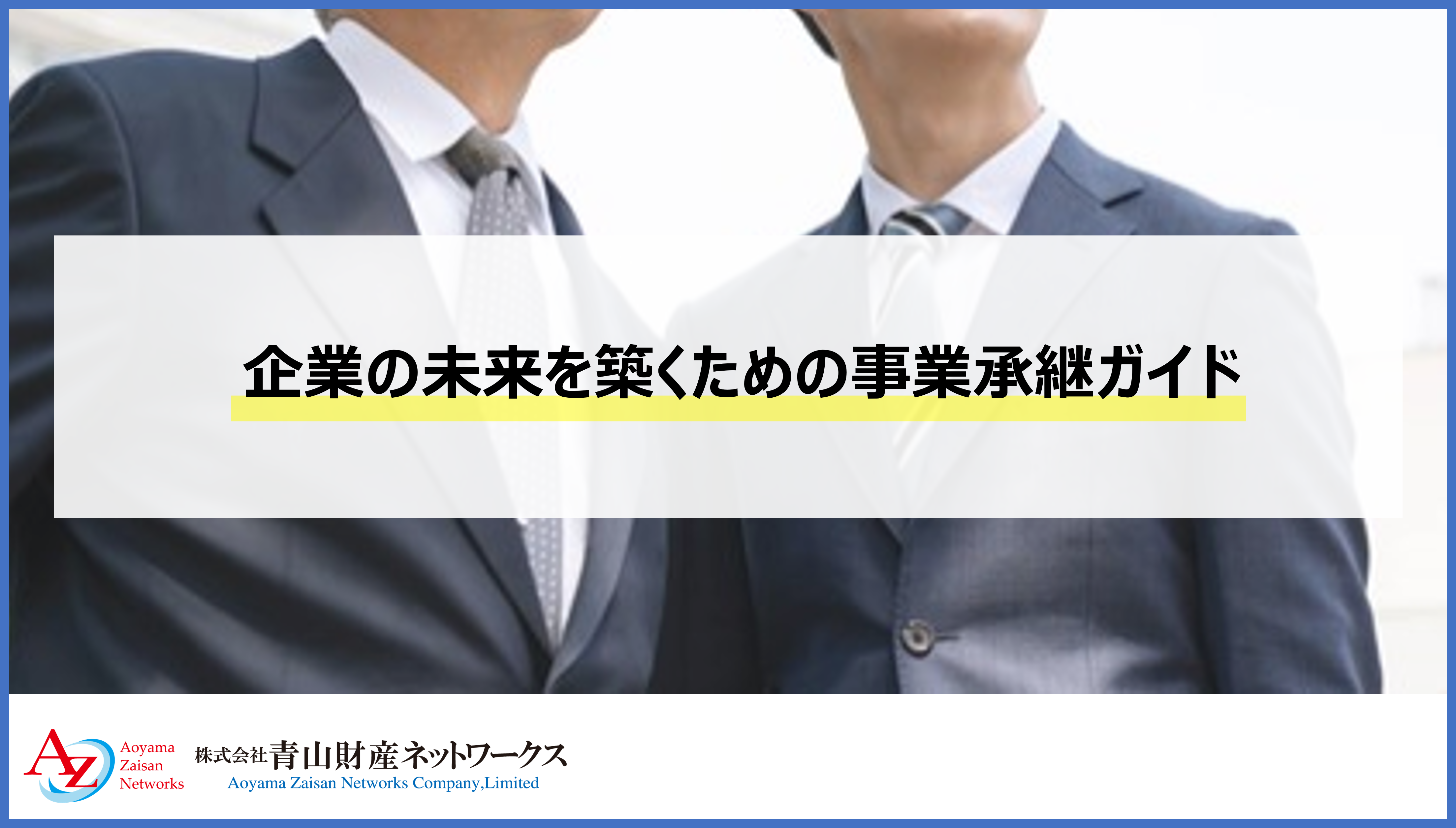自分の親など親族が会社を経営している場合、あるいは自分自身が会社を経営している場合に直面する可能性があるのが、「会社の相続」という問題です。
会社を相続するには、様々な手続きを踏んでいく必要があります。また、相続人が複数の場合、相続人同士の関係性によってはトラブルが発生する恐れもあります。このように会社の相続は簡単ではないので、早い段階から準備をしておくことが大切です。
そこでこの記事では、会社の相続についての基本的な概要から、会社を相続する流れ、会社相続で発生する可能性があるトラブルの例、相続トラブルを回避するためのポイントなどについて解説していきます。
そもそも「会社の相続」とは?

親などの親族が亡くなった場合、遺産相続が発生する可能性があります。その遺産相続において、「会社の相続」とはどのようなことを言うのでしょうか。まずは、会社の相続についての基本的な考えから確認していきましょう。
会社の相続=株式の相続
「会社の相続」とは、「会社の株式を相続すること」です。
自分の親が会社の経営者である場合、親が亡くなると保有していた資産の相続が発生します。相続資産となるのは、現金や不動産などに加え、経営していた会社の株式も対象です。株式とは株式会社が発行する有価証券であり、株式を保有している株主が亡くなると、その株式は相続人に引き継がれます。相続人は遺言書や遺産分割協議、法定相続分などを基準に決定され、相続人に選ばれた人には株式を含む資産の全部または一部が相続される仕組みです。
ただ、会社を相続する際には様々な手続きが必要で、配偶者や子などの法定相続人であっても簡単に後継者になれるわけではありません。会社の相続は、前の経営者が所有していた株式を後継者が相続することで実現します。ただ、会社の経営権を握るためには一定以上の割合の株式を保有する必要があります。
会社の定義と個人事業主との違い
会社とは、株式会社や合同会社といった法人格を有する組織を指します。法人の経営者は法律上、実際の人と同じように独立した人格を持つ存在として扱われます。法人は経営者の個人的な所有物ではないため、経営者が亡くなっても、法人そのものは相続対象になりません。同様に、代表取締役といった地位の相続も不可能です。会社の財産についても、経営者の所有物ではないため、相続の対象ではありません。
会社組織ではなく、個人事業主として事業を営む形態もあります。個人事業主の事業用財産は、会社ではなく個人に帰属する点が特徴です。そのため、相続の手続きは個人間の相続と変わらず、資産や負債を相続人がそのまま相続することになります。その一方で、個人事業の各種届出は必要です。まず、亡くなった前経営者の廃業届を、後継者が税務署へ提出します。そして、後継者が新たに開業届を提出することで、個人事業の相続は完了です。
会社相続の流れ(法人の場合)

会社の種類は、株式会社や合同会社などの法人と、個人が経営する個人事業の2つに大きく分けられます。こちらでは、法人を相続する場合の基本的な流れについて紹介していきます。
株式の相続(贈与)または譲渡
法人の場合、会社の相続は「後継者が自社株を相続して会社の経営権を掌握する」こととされています。そのため会社の相続でまず着手すべきなのは、亡くなった前経営者が保有していた株式の相続手続きです。
株式は、保有割合によって会社に対して行使できる権利が変わります。会社の経営権を手にするには過半数の議決権を得なければならないため、後継者になるためには最低でも過半数の株式が必要です。また、会社にとって重要な事項を単独で可決するには、全体の3分の2以上の株式を取得しなければなりません。よりスムーズに会社経営を行うためには、後継者が全ての株式を相続することが理想と言えます。
株式の名義変更
会社の株式は、取得しただけでは議決権の効力を発揮しないもの。議決権を行使するためには、株式名簿の名義を前経営者から後継者に変更するというプロセスを経なければなりません。
また、同時に「株券発行会社か不発行会社か」を確認することも大切です。株券発行会社の場合、株主名簿の変更だけではなく、実際に株券を取得しなければ手続きは完了しません。
代表者の決定および地位の確保
前経営者からの株式の相続が成立しても、取得しただけでは立場上はあくまで経営者ではなく、大株主に過ぎません。後継者として経営を行うためには、会社の代表取締役に就任する必要があります。
取締役会がある会社で代表取締役になるための手順は、後継者はまず株主総会を開いて取締役として選任され、その後、さらに取締役会にて代表取締役に選任されるという流れです。取締役会が設置されていない場合は、株主総会の決議などを経て代表取締役に就任することになります。
代表取締役の地位を確保したら、法務局にて登記を行い、税務署などへの代表者変更手続きなどの各種変更手続きを行うことで、会社の相続は一旦完了した状態になります。さらに、スムーズに事業へ取り組んでいくためには、代表取締役が交代したことを取引先などへ通知することも重要です。
会社の相続でよくあるトラブル
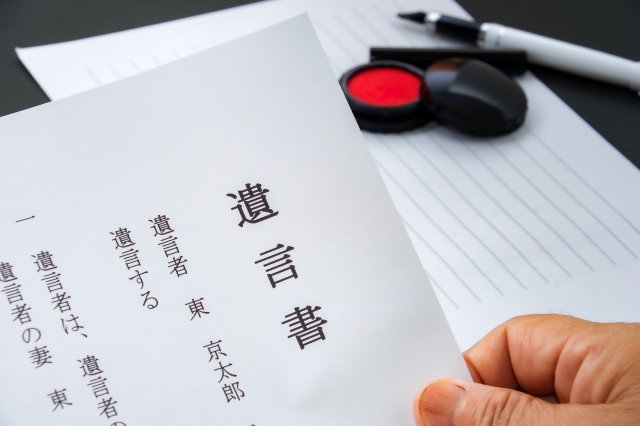
親族から財産を相続する際、相続人の不合意や、負債などによるトラブルが発生することも珍しくありません。こうしたトラブルのリスクは、会社の相続においても同様です。こちらでは、会社の相続で発生する可能性があるトラブルについて見ていきましょう。将来、会社相続の当事者になる可能性がある方は、参考にしてください。
取得した株式の数によっては経営権を掌握できない
会社の相続では、後継者が経営権を取得することが大切です。発行株式の全てを相続することができれば、「経営者の意志=株主の意志」となるため、他の株主への対応に関する心配は無用になります。全てではなくても、全体の3分の2以上の株式を取得できれば、事業譲渡の承認、合併など会社の重要事項を単独で決めることが可能です。
しかし、兄弟が多いなど法定相続人が複数いる場合、会社の経営者となるのに十分な数の株式が集まらない状況も想定されます。このように、相続の仕方によっては会社の経営権を掌握できない恐れがあるため、当事者は注意が必要です。
相続人同士で衝突してしまう
親族間で後継者になることを希望する人が複数いると、相続人同士で争いに発展する可能性があります。またスムーズに経営権を移譲するために特定の1人へ大多数の株式を保有させる場合にも、相続財産の金額の不均衡から、不満を持った相続人が相続を認めずに手続きが難航するかもしれません。
後継者選びやそのための株式の扱いによっては、相続人の間で衝突が発生する恐れがあります。当事者になる可能性があるのなら、前もって話し合いを進めるなどの対応策が必要です。
負債も相続する可能性がある
会社が金融機関などから融資を受けていることは珍しくありません。特に中小企業では、経営者が会社の連帯保証人になっていることがあります。前の経営者が会社の保証人になっていた場合、後継者は保証債務も相続することになるため注意が必要です。
会社の経営が順調で、借入金を返済していれば問題はありません。しかし、経営状況が悪化して返済が滞ってしまうと、会社の保証人である後継者に、個人としての返済義務が生じることになります。会社の相続では、負債も相続するというリスクが発生する可能性があることを、あらかじめ理解しておくべきだと言えるでしょう。
会社の相続トラブルを避けるには
会社の相続には、上記のように様々なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。ただ、あらかじめ対応策を講じておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。こちらでは、会社の相続トラブルを避けるためのポイントについて紹介していきます。
遺言書を作成し、後継者以外にも財産を平等に相続させる
通常の遺産相続では、相続人が3人兄弟の場合、財産を3等分して相続することになります。そうなると、後継者に株式を集めることは難しくなってしまいます。そこで有効なのが遺言書です。
遺言書に記載した相続分は、法定相続分よりも優先されます。前任者が後継者として希望していた人物に株式を相続させることができるため、会社の相続をスムーズに進められるようになるでしょう。
遺言書の内容が優先されるとは言え、法定相続人には遺留分が認められているもの。相続人同士で揉めないためにも、後継者以外の相続人の遺留分に配慮しながら遺言書を作成することが重要です。
遺言書は、正しく作成しないと効力を発揮しない恐れがあります。そのため、作成にあたっては、遺産相続の専門家に相談しながら進めると安心です。
生前贈与での事業承継
財産を持っている人が、生存中に親族に対して財産を相続するのが生前贈与という仕組みです。その生前贈与を利用して、後継者として考えている人物に株式を移し、事業承継を進めていくという手段もあります。
生前贈与では経営者が現役のうちに事業を引き継ぐことができるので、実践的に経営者としてのノウハウを蓄積できることがメリットです。
贈与財産の金額によって贈与税が課税されますが、状況によっては事業承継税制という相続税・贈与税の納税猶予が受けられる制度を活用できます。
家族信託を行う
家族信託とは、現在の経営者が持つ財産の管理を、後継者となる親族に任せる制度です。自社株式の管理や運用、処分は後継者が担い、議決権行使も行います。一方、生じた利益は経営者である親が取得する仕組みです。将来的に経営者が亡くなれば、自社株式は後継者がそのまま承継することになります。
まとめ
会社を子など親族に引き継ぐ際、株式の相続という手段を取ることができます。ただ、後継者とそれ以外の相続人との間で遺産分割のトラブルが発生する可能性があるなど、注意すべき点はいくつかあります。会社の株式を相続する際には、直面するリスクをあらかじめ把握し、入念に準備を進めていくことが大切です。
株式の相続自体、プロセスが複雑で、相続税や贈与税など税金の問題も絡むため、対応するには専門的な知識が必要です。スムーズに相続の手続きを進めたいのであれば、相続や事業承継などに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
青山財産ネットワークスの特徴
青山財産ネットワークスでは、税理士、司法書士など、国家資格を有する専門家が150名以上在籍し、30年以上の豊富な実績に基づき、お客様のご希望に沿って、相続、事業承継、財産の承継・運用・管理に関する様々なご提案をしております。お客様とその親族の方々にとって最良の結果になるようプランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
監修者
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~