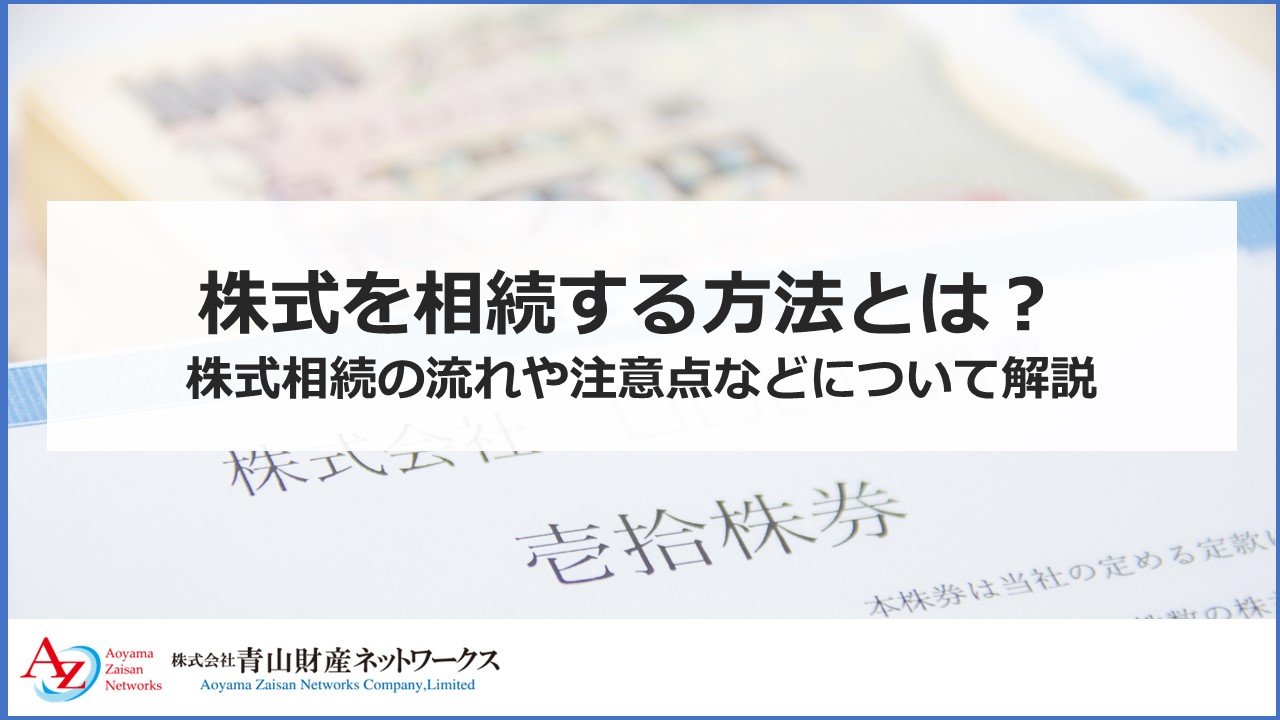企業経営者の中には、将来的に自分の子などの親族に経営を任せたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。ただ、企業の経営を引き継ぐには、自社株の承継というプロセスが必要です。
自社株を後継者に譲ることは、財産を相続することでもあります。相続は、経営者の親族を巻き込んだ問題です。さらに、株式は財産であり、相続すると相続税が発生します。このように、事業を承継するにあたって、自社株の扱いが課題となり頭を悩ませるケースも珍しくありません。
そこでこの記事では、自社株を後継者に相続する流れや、自社株の相続でよくあるトラブル、自社株をスムーズに相続するポイントなどについて、解説していきます。
自社株の相続で経営を引き継ぐプロセス

自分が経営している企業の株式を自身の子など親族に相続すると、経営をそのまま引き継がせることが可能です。では、自社株の相続はどのように行われるのでしょうか。まずは、自社株の相続および経営者の交代のプロセスについて見ていきましょう。
株主の状況の調査
自社の株式について、誰がどれほどの株数を保有しているのか調査するところから始まります。株式は、被相続人となる経営者だけではなく、役員や従業員、あるいはその他の人が保有している可能性が考えられます。経営者が交代した場合、以前と変わらずそのまま経営が続けられるという保証はありません。
そのため、後継者が会社を引き継いでからも安定経営ができるよう、相続が発生する前に株式の保有状況を調査し、株主との話し合いや株式売却の交渉などを行うことがあります。
株式の評価額の算出
株式を相続する場合、相続税の金額を決めるために、株式の評価額を算出する必要があります。上場企業の場合は、株式市場で取引されている金額が評価額です。一方、非上場企業の場合は公的な価格がないため、類似業種比準方式や純資産価額方式などの方法で算出します。
自社株を相続する
経営者が亡くなった時点で、相続が発生します。遺言書が残されている場合、遺産は基本的に遺言書の記載の通りに配分されます。一方、遺言書がなければ、全ての相続人によって遺産分割協議が行われ、株式を含めた遺産を分ける決まりです。相続の前に後継者が決まっている場合、遺言書に全ての株式を後継者に相続させることを記載しておけば、自社株の相続はスムーズに進む傾向があります。そのため、遺言書の有無は、自社株の相続において非常に重要な要素と言えるでしょう。
株式の名義変更
株式は株主名簿の書き換えが完了してはじめて、株主総会の決議における議決権が生まれます。そのため、株式を相続した後継者は、株主名簿の名義変更も必要です。会社が株券発行会社であれば、実際の株券を取得します。
株主総会での手続き
株式の相続・移転が完了しても、自動的に後継者が代表取締役になるわけではありません。株主総会または取締役会で後継者が新しい代表取締役として選任されることで、経営者としての役割の引き継ぎが完了します。
自社株の相続でよくあるトラブル

相続関係では、何かしらのトラブルが起こることは珍しくありません。その中で、自社株の相続で発生する恐れがあるトラブルについて見ていきましょう。
親族間での話し合いが難航
被相続人が遺言を作っていない場合、相続人全員による遺産分割協議で相続財産の配分を決めることになります。株式も相続財産のため、兄弟がいる場合、誰が後継者になるのかを決めていないと後継者の座をめぐって争いになる恐れがあることは、注意しておきたいポイントです。
また、遺産が自社株のみの場合、引き継がれる会社に関わらない相続人にとって株式は「意味がないもの」と捉えられることもあります。不平等な財産分与になり、当事者間で問題が発生するかもしれません。
後継者が相続税を払えない
遺産を相続した人は、基本的に相続税を納めます。相続税には基礎控除があり、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税を払う必要はありません。ただし、基礎控除額を超えると相続税が発生します。
相続した自社株が高く評価されると、比例して遺産の総額も高くなる仕組みです。そうなると相続税が高額になるため、後継者が相続税を支払えないリスクが考えられます。
経営権を握るための株数を確保できない
企業経営において、後継者が議決権の2/3以上を所持しているかどうかが、後継者による安定した経営を行えるかどうかのポイントとなってきます。しかし、相続人が多ければ遺産相続で株式が広く分散し、後継者が経営権を確保するに足る株式を保有できなくなってしまいます。そうなると、他の相続人が影響のある株主として経営に意見することも可能なので、後継者にとっての安定経営に支障が出る恐れがあります。
負債も相続の対象となる
中小企業の場合、融資を受ける際に、経営者が個人名義で保証人になっていることは珍しくありません。経営者が会社の保証人になっていた場合、相続した後継者が保証人の立場も引き継ぎます。さらに、未払いの賃金などがあった場合、その支払い責任も後継者が負うことになります。このように、自社株を相続することで、その会社が持つ負債も引き継ぐことになることは、あらかじめ理解しておきましょう。
自社株の相続を円滑に行うためのポイント
経営者が自社株を後継者に相続するためには、複雑なプロセスを踏んでいく必要があります。こちらでは、できるだけスムーズに相続を行うために知っておきたいポイントを紹介します。
遺言書を作成する
経営者である親が遺言書を残していない場合、財産は法定相続人によって相続される決まりです。この場合、法定相続人が多いと株式が複数名に分散してしまい、後継者が経営権を取得できない恐れがあります。
経営者が後継者として考えている人物に自社株を相続させるためには、遺言書を作成しておくことが必要です。遺産相続は遺言書の内容が優先されるため、後継者が確実に自社株を引き継ぐことが一般的です。
遺留分も十分に配慮する
経営者は遺言によって後継者に自社株を集中させることはできるものの、他の相続人がいる場合は「遺留分」を確保しなければなりません。
遺留分とは、法定相続人が得る権利を持つ最低限の相続財産のことです。親が「全財産を後継者に相続させる」という遺言を残しても、遺留分という仕組みがあるため、後継者以外の相続人は遺留分を請求できます。
後継者に自社株が集まらなければ、安定した経営はできません。そのため、後継者が全ての自社株を相続する代わりに、他の相続人には現金などの資産を相続させる、といった配慮が重要になってきます。
生前贈与を行う
生前贈与とは、本人が存命中に他者へ財産を分け与える取り組みです。経営者がまだ健在なうちに自社株を後継者に贈与しておけば、後継者は経営権を掌握するに足りる株式を確実に得られるため、自社株の相続において有効な手段とされています。
贈与を行うと贈与税が発生しますが、暦年贈与では年で110万円の控除が適用されます。これは、贈与の総額が年間110万円に達しなければ、贈与税はかからないという税制 です。同様に、相続時精算課税制度においても、年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告は不要です。なお、贈与加算の対象であれば、贈与の総額が年間110万円に達しない場合でも相続税はかかるためご留意ください。
早めに相続税を納める準備をしておく
株式を含む遺産の価値が高く評価された場合、相続した人が納めるべき相続税の金額も大きくなります。相続税の額が大きい場合、後継者は税金の支払いが困難になってしまうかもしれません。このように、自社株を相続することによって、後継者が資金的に苦しくなる可能性も考えられます。
そのためにも当事者となる可能性のある人は、将来を見据えて多めに貯蓄しておく、金融機関から融資を受けるなどの、相続に向けた取り組みをしておくといいでしょう。
事業承継税制で自社株の相続を円滑に

自社の経営を誰かに承継する際には、後継者に大きな税負担が生じることが想定されます。そこで設けられたのが、事業承継税制という仕組みです。こちらでは、事業承継税制の概要や適用を受けるための要件、さらには注意点について解説していきます。
事業承継税制の概要
事業承継は、会社の経営権や資産を誰かに引き継ぐ取り組みです。経営者が事業承継を行う場合は、後継者に相続税または贈与税が課されるため、税額によっては円満に経営を引き継げない恐れがあります。
こうした状況を鑑みて創設されたのが、事業承継税制です。この制度では、経営の後継者が企業の株式を相続や生前贈与で引き継ぐ際、相続税や贈与税について納税が猶予されます。さらに、一定期間要件を満たすと、最終的に猶予された税額は免除されます。
事業承継税制の適用を受けるための要件
自社株の相続という点から、法人向けの事業承継税制の適用を受けるための要件を紹介します。
◎会社の主な要件
- 中小企業である。
- 常時使用する従業員が1名以上在籍している。
- 上場会社ではない。
- 風俗営業会社ではない
- 資産管理会社ではない(一定の要件を満たす場合を除く)。
◎先代経営者の主な要件
- 会社の代表だった ことがある。
- 相続・贈与の直前に、先代経営者の親族などで過半数以上の株式を保有し、かつ筆頭株主でもあった。
- 贈与時に代表を退任している(贈与の場合)。
◎後継者の主な要件
- 相続または贈与時、後継者と後継者親族などで総議決権数の過半数を保有し、さらに親族の中で筆頭株主である。
- 18歳以上で贈与の直前までに役員に就任しており、会社の代表である(贈与の場合)。
- 相続の直前に役員を務めており、かつ相続してから5ヶ月後に代表者である。
納税猶予の取り消しがあるので注意
事業承継税制は、納税猶予している期間中、所定の手続きと一定の要件を満たし続ける必要があります。納税猶予を継続するためには、最初の5年間は年次報告書については都道府県、継続届出書については税務署へそれぞれ提出します。5年が経過してからも、3年に1度は税務署に継続届出書を提出する必要があり、守られなければ納税猶予が取り消されてしまいます。このように、事業承継税制による納税の猶予は取り消される可能性があることは注意しておきたいところです。
まとめ
会社の経営を自分の子などの親族に引き継ぐ際には、自社株の相続という手段があります。経営者が保有する株式を後継者に承継するという作業ではありますが、経営者と後継者だけではなく後継者以外の相続人も関わってくる問題です。また、遺言や相続税および贈与税といった税金、遺留分など、注意すべき点も数多く存在します。
複雑で専門知識も必要な自社株の相続では、相続や事業承継に精通した専門家は心強い味方です。豊富な経験を持つプロであれば、状況に応じて的確な対応をしてくれます。円滑な自社株の相続を目指すのであれば、専門家を頼ることを検討してもいいでしょう。
青山財産ネットワークスの特徴
青山財産ネットワークスでは、税理士、司法書士など、国家資格を有する専門家が150名以上在籍し、30年以上の豊富な実績に基づき、お客様のご希望に沿って、事業承継、財産の承継・運用・管理に関するさまざまなご提案をしております。お客様とその親族の方々にとって最良の結果になるようプランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~